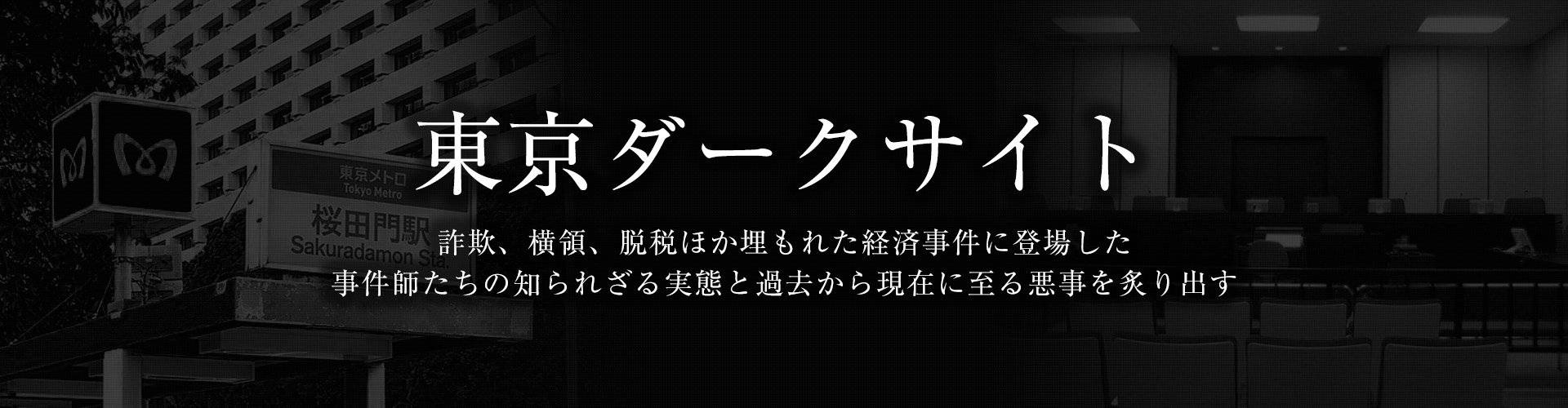〔鈴木の嘘を増幅させた弁護士、見逃した裁判官〕
鈴木義彦が親和銀行不正融資事件で逮捕されたのは平成10年5月31日で、起訴はされたが、親和銀行との和解が成立したことで判決は執行猶予となった。銀行との和解は、鈴木が不正に受けた融資金(判明している分だけでも総額で数十億円といわれていた)の一部約17億円を返済することで成立したのだったが、その資金は西義輝、そしてA氏との三者で交わした「合意書」に基づいた株取引で得た利益金から流用された。しかし、その事実がA氏や西に知らされることはなかったから、これは鈴木による横領そのものだった。
17億円という和解金は被告の身であった当時の鈴木にとっては、どうやっても単独で調達できるものではなかった。もちろん、鈴木はエフアールの代表取締役を辞任していたから表向きにも関係することはできなかった。しかも、時期はずれるが、鈴木が山内興産の社長、末吉和喜を騙して預かった「タカラブネ」株200万株(20億円相当)の返還をめぐって起こされた訴訟でも和解交渉を進めていた鈴木は、末吉に対して約4億5000万円の返済を提示して和解に持ち込んだ。その資金もまた株取引によって得た利益金が流用された。鈴木は利益金が無ければ身軽になることはできなかった。そうした“恩恵”を鈴木は独り占めしつつさらに利益金の独り占めを謀ったのである。
鈴木と西が株取引で最初に取り組んだ銘柄は「宝林」であったが、これが約170億円という予想外の利益を上げたことが、その後に起きるいくつもの深刻なトラブルの火種になったのは今さら言うまでもない。鈴木が利益を占有し受益者排除を徹底したために、その後も株取引を継続する中で利益金は鈴木の懐の中で膨れ上がる一方となったが、しかし、株取引で共闘していたはずの西義輝は自殺に追い込まれ、鈴木の側近としてクロニクル(旧なが多、エフアール)をけん引してきた天野裕が都心の京王プラザホテル客室で不審な死を遂げた。鈴木のもう一人の側近だった大石高裕は交通事故で死亡したほか、行方知れずとなった関係者はそれこそ数知れない、というのが実情なのである。仮にその一つでも全容が解明されれば、鈴木を巡る状況は明らかに大きく変わる。
A氏による貸金返還請求訴訟は平成27年7月に提起され、平成30年6月の一審判決を経て同年11月28日の二審判決で幕を閉じた。しかし、一審、二審ともに鈴木の利益占有の実態が暴き出されることも無ければ、前述したような鈴木の周辺人脈が相次いで行方知れずとなり、あるいは不審な死を遂げた真相に迫る手がかりすら封じ込められたと言っても過言ではない。それどころか、審理の場では、代理人弁護士が増幅させた鈴木の嘘を6人の裁判官までもが罷り通らせてしまったのだ。
本誌がサイトの公開以来、現在も継続して鈴木の「偽証」に迫っているのは、まさに鈴木の利益占有が数多くの犠牲者を生んでいる実態の解明に他ならない。
なお、前号の記事で一部補足する必要があるので、それに触れておくが、鈴木による虚偽証言で重要と思われる3点を列記した中で、鈴木が親和銀行不正融資事件で逮捕される直前3日前の5月28日の時点で、鈴木はそれまでにA氏から借用した約28億円の債務を1円も返済していなかったばかりか、さらに8000万円を借り受けた。これから逮捕されるという人間に、仮にそれが弁護士費用であろうが生活支援金であろうが、貸し与える人間は絶対にいないと関係者は口を揃える。しかし、鈴木はそれさえも見事に裏切ったうえに審理の場では嘘で塗り固めた証言により裏切りをさらに繰り返したのである。
また、A氏に言い値で買ってもらったピンクダイヤモンドと絵画についても、鈴木は審理の場では、その前年の10月15日に借り受けた3億円の金銭借用書を合致させるという有り得ない主張を展開したが、この金銭借用書の「但書」には3億円を借り受けるに当たっての担保が明記されていた。そうした事実を裁判官はことごとく無視して、ピンクダイヤモンドと絵画、そして高級時計に係る債権7億4000万円を認めなかったのである。
鈴木は、「合意書」の有効性を認めた平成18年10月16日の、A氏と西義輝との協議の場について、審理では「(A氏や西に)強迫され、『和解書』に署名指印して分配金の支払約束をしなければその場を収めることができないと思った」という証言を繰り返したが、協議の場では全く逆の暴言を鈴木は吐いていた。それは、西に対して「お前、ここで死ねば……、お前にその度胸があるのか」という言葉だった。強迫されたと証言した人間が、実際には脅迫したという人間を恫喝していたのである。このやり取りも、録音テープが証拠として提出されていたが、裁判官は無視してしまったのである。いかに訴訟の判決が理不尽で、裁判官による事実認定の誤りが判決の全てに及んでいるかが分かるのではないか。(以下次号)