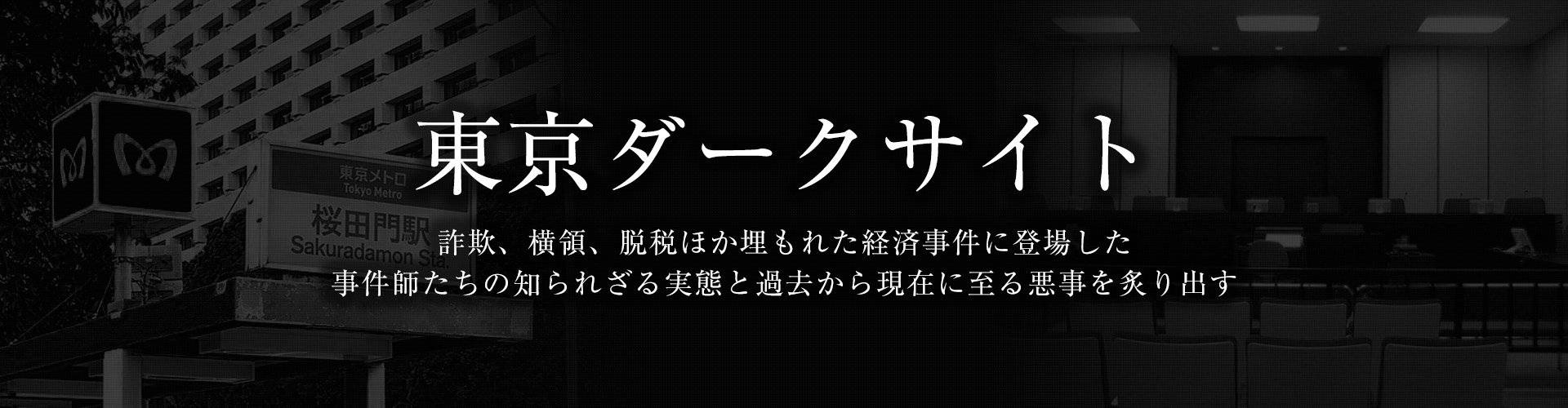〔高裁判決は地裁判決の誤字脱字を修正のみ〕
貸金返還請求訴訟において、鈴木は平成9年9月から同10年5月28日までの期間で発生した債務約28億円(ダイヤモンド、絵画、時計等の詐欺、横領分を含む)について、平成11年9月30日付でA氏が鈴木に対して交付した「確認書」をもって「債務は完済された」と主張した。
(写真下:ピンクダイヤモンドと絵画の販売受託を示す念書)

dav
手形原本をエフアールに預けるのは2度目であったので、A氏は問題はなかろうと了解したが、さらに債権債務は無いとする「確認書」も欲しいという鈴木からの依頼があった。この手形の預け依頼は、2度ともA氏と天野、鈴木の間に入った西が行っており、特に「確認書」の交付についてA氏は西に「大丈夫なのか?」と確認し、西が問題はないことを証するため「手形原本の預けと『確認書』交付はエフアールの決算対策のために鈴木の要請によるもので、債務は返済されていない」旨を記した「確認書」を別に作成して当日A氏に渡していた。
A氏は同じ趣旨の「確認書」を西の会社(東京オークションハウス)にも交付したことがあったために躊躇はしたが「確認書」の交付に応じた。西が手形原本と「確認書」をA氏から預かり鈴木に渡した後、鈴木からA氏宛に「無理なお願いをして申し訳ありません。本当に有難うございました」と礼を述べる電話があった。
そうした経緯がありながら、株取引の利益分配でA氏と西、鈴木の関係に溝ができ深刻な対立が起きると、鈴木は一切返済していない債務約28億円を反故にする為に「確認書」を持ち出した。鈴木が裁判で証拠として提出したのが唯一この「確認書」で、このことだけでも鈴木の言動が嘘であることが明確に分かる。
また、「合意書」に基づいた株取引を行った事実も認めず、「和解書」についても交渉で平林が主張した“強迫”と“心裡留保”を根拠にして、それを裏付けるような虚偽の出来事を陳述したのであったが、虚偽であることを裏付ける証拠も多く見つかっている。
貸金返還請求訴訟で裁判官は「合意書」については、鈴木が宝林株での株取引があったと認めたにもかかわらず、それに基づいた株取引が実行された証拠がないとして認めず、したがって「和解書」も無効だとする判決を下した。鈴木が認めた部分さえ証拠と捉えず、納得のいく説明がないまま終了した。
A氏は、当然ながらそれを不服として控訴した。しかし、控訴審の裁判官は審理もろくに行わず、誤字脱字の修正のみで地裁判決を丸ごと支持する形でA氏の主張を退けた。
地裁判決によると、「株取扱合意において定義されるべき分配対象利益の内容及び範囲は、余りに無限定というべきもの」であり、「被告に対して法律上の具体的な義務を負わせる上で最低限必要な程度の特定すらされていないものといわざるを得ない」という判断をした。
裁判官が、「合意書」の体裁や文言の定義づけに拘るのは仕方が無いとしても、鈴木の証言や主張は場面が変わるに従って、どんどんひどく変転した。A氏、西との対応や発言、鈴木が所在不明となって以後の平林と青田の支離滅裂で不当な主張、そしてそれを裁判ではさらに増幅させた。裁判官は、そうした鈴木の主張や証言の変転に何ら目を向けなかったのは何故か。
平成18年10月16日に和解書を作成した三者協議の後、鈴木は頻繁にA氏に電話を架け、「西の買い支え損は約70億と言っていたが、正確にはいくらか?」と尋ね、それを確認して「全体の利益より引いて3等分しないといけませんね」と鈴木はそこまで「合意書」の有効性を追認した。また1週間後の10月23日、鈴木が三たびA氏の事務所を訪れた。これほど立て続けに鈴木が姿を見せるのは珍しかったが、「和解書」で約束したA氏と西それぞれに25億円を支払うことと、その後2年以内にA氏に20億円を支払うことについて、より具体的な説明をした。鈴木は、少なくとも「不正があれば利益の分配は受けられない」ことが「合意書」に明記されていたからこそ「和解書」でも不正を認め、金額50億円の支払を提示したことが容易に推察される。それ故に“強迫”や“心裡留保”など根拠になりようがないのに裁判官はあっさりと採用してしまったのである。
鈴木のように二転三転するような証言を裁判官が証拠として採用することはない、というのが裁判官による認定の通例であるにもかかわらず、ほとんどが虚偽の証言を裁判官は「合意書」と「和解書」の無効を理由にして、「(鈴木が)明確に意思表示した事実は認められない」と判断する一方で、西が「株取引の利益」と言って持参した15億円、鈴木が持参した10億円をA氏への返済金と断定してしまったのは、あまりに不可解で、誤審といわざるを得ず、判決は誰が見ても誤りとしか言いようが無い。
原告の主張を裏付けるべき証言が必須だったはずの西義輝が平成22年2月に自殺し、「合意書」に基づいた株取引の実態を、説得力をもって裁判官に訴えることができなかった点は大きかった。
西はA氏に決定的な裏切りを働き、鈴木に言われるままA氏と鈴木の間の距離を意図的に作り出し、平成11年7月30日に15億円の利益金をA氏に納めて期待をさせながら、それ以後の株取引で利益が出ているのにもかかわらず、西は具体的な報告も実情も語らないままA氏から株価の買い支え資金を引き出し続けたのである。それ故、A氏が当事者として「合意書」や「和解書」の作成経緯を法廷で正当性を訴えても、裁判官の思い込みを排除することは叶わなかった。(以下次号)