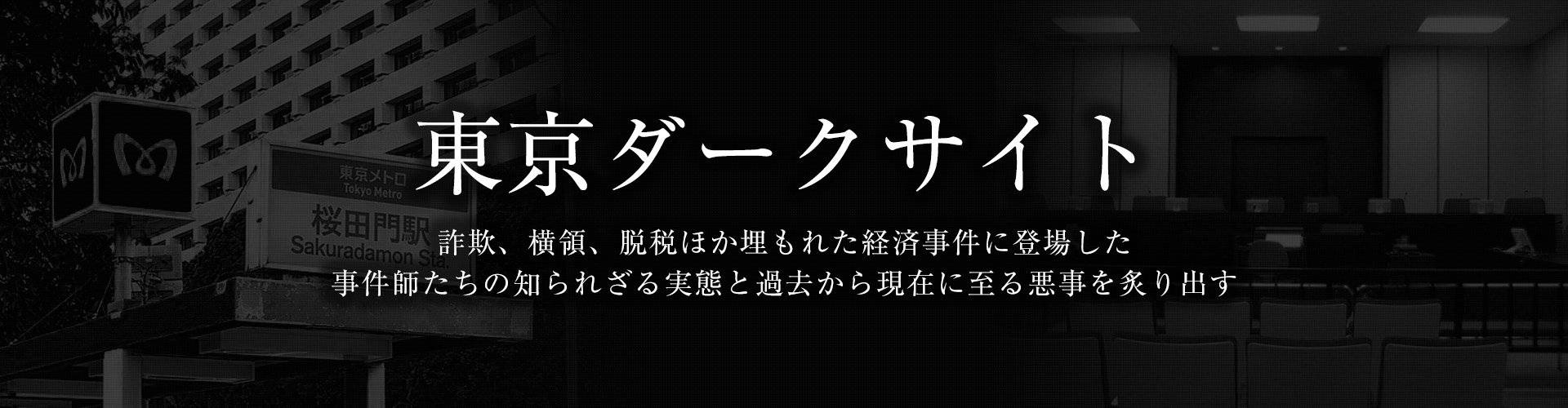《「仏の顔も三度まで」と言うが、A氏の生家は「仏」という屋号がついていて、困った人から頼まれると手を差し伸べる伝統が先祖の時代から息づいているらしい。鈴木と西がA氏から助けられたのは三度どころの話ではない。西は世話になったまま自殺してしまったが、鈴木は、逃げ回っていて一銭も返さず、A氏の物である莫大な資産を隠匿している。「地獄のサタン(悪魔)も金次第」と言うが、あれは嘘だ。死んだときに渡る「三途の川の渡し賃は六文」だそうだ。いくら悪銭を沢山持っていても三途の川は渡れないという。今のままでは生きることも死ぬこともできない。お前は、家族と一緒に生き地獄で暮らすしかなさそうだ》
《鈴木のA氏からの借金は約28億円だが、金利を年15%で計算すると平成14年6月の時点で既に40億円を超えていた。平成9年当時、鈴木は10日で1割以上の金利でも借りられるところが無く、「年36%(遅延損害金年40%)でお願いします」とA氏に懇願した。この計算では70億円以上になった。それを西が「今後の株取引で利益が大きくなる」と言ってA氏に頼み込み25億円にまで圧縮してもらった。当然、西の依頼は鈴木の指示に違いないが、その後の裁判で鈴木は「(平成11年9月30日に)完済したので借金は全くない」と主張している。鈴木からFRの決算のために助けてほしいと言われ、A氏が便宜的に「債権債務はない」とする確認書を作って上げたが、これが鈴木側の唯一の証拠だった。また合意書破棄の礼金として西に渡した10億円も平成14年6月27日のA氏との面談の際にA氏への返済金の一部として渡したものと偽ったばかりか、その後の裁判では「西に渡したとは言ってない」とか「その日は3人で会っていない」とまで主張したが、同日には間違いなく会っていて、鈴木の15億円、西の10億円の借用書には確定日付がある。こんな大事な書類を鈴木は忘れていたというのか。確定日付まで取ってある借用書をそんな意識でしか考えていなかったから、その場しのぎの嘘を重ねた分、裁判での主張が二転三転する。鈴木はそういう人間だと思う。しかし桁外れの異常な感覚で社会を渡っていける訳がないし、こんな悪質な鈴木の主張を裁判官が疑問視しなかったことが不可解でならない》
《裁判で確定した判決について一定の要件を満たす重大な理由がある場合に再審理を行う事が出来る。民事訴訟でも判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立が出来る。「判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと」や「証人・鑑定人・通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと」、また「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと」等が判決の不当性の根拠になるはずだが、裁判所は消極的あるいは対抗的態度を取って再審を妨害するようなことがあってはならない》
《仏教では、人間が恐怖に慄いたり(おののいたり)全身冷や汗をかいたりすることは、過去に他人を苦しめ、悲しませ、酷い目に合わせて来て、悪の限りを尽くして来た証拠であると言われている。髪の毛や、骨の中までひどく恐れを感じるらしいが、鈴木も恐らく夜な夜な悪夢を見て恐怖に慄き、冷や汗を流している事だろう。これは、長谷川元弁護士や青田も同じだろう》
《宝林株を取得した際に金融庁に提出した「大量保有報告書」だが、虚偽記載があったとはいえ正式に提出されている以上金融庁に記録は残っている筈だ。デジタル化された現在では簡単に閲覧も出来るだろう。勝手に名前を使われた紀井氏の証言もあり、疑惑に大きく関わっている鈴木を追及する国税庁や金融庁、捜査機関にとって報告書は有力な証拠の一つとして捉えられるし、動きが活発化するきっかけにもなる》
《A氏側より裁判の不当判決を是正するための対応を求める書簡が最高裁判所長官をはじめ品田、野山両裁判長に送られたようだが、制度上一度確定した判決を覆す事は出来ないらしい。しかし既に判決が下された裁判であっても再審を訴える条件(民事訴訟法338条1項柱書の同項9号)の「判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があった場合」に明らかに抵触するとみられるので、再審請求を認めて、改めて審理をやり直すべく「合意書」と「和解書」の無効の認定を一旦取り消すべきだろう》(取材関係者より)
《この記事を読んで、裁判というものに大きな疑問を抱き、少し調べてみた。ごく基本的な事だけを抜粋して以下に書くと、民事裁判は、通常、当事者間で財産上の請求をしたり、されたりするものをいう。民事裁判の当事者は、原則として国の機関以外の者(私人)になり、訴えた方が「原告」、訴えられた方を「被告」と呼ぶが、刑事事件の当事者は、被害者が加害者と思われる人間を告訴して国の機関に捜査してもらうことで始まる。ここでの当事者は国の機関(警察官、検察官等)と犯人(法律上、裁判になる前は被疑者、裁判になってからは被告人と呼ばれる)」となり、被害者は刑事裁判の当事者ではないということになる。ただ、民事裁判と異なり、訴えるのは必ず国の機関である検察官となり、犯人は訴えられる立場の「被告人」になる。民事裁判も、刑事裁判も裁判官が審議した結果、判決を出して紛争を解決する点は共通している。しかし、その判決を実現する手続きには違いがある。刑事事件の場合、被告人に対して有罪判決が出た場合は検察官勝訴判決となり被告人を処罰する手続きが刑の執行になる。民事裁判の場合は、原告が被告に金銭の支払いを求め、原告勝訴の判決が下された場合、その判決を実現する手続きは民事執行手続きになる。簡単に言うと被告が判決に従わない時は、国が被告の財産を強制的に処分したり、差し押さえをして原告への支払いに充てることが出来る。しかし、今回の様に、原告が敗訴となった場合、法的には裁判は終結したという事になるが裁判官の判断が正しかったかどうかという問題が残り、新たな裁判に発展する可能性が大である。この様に、検察官が告訴した時点で99%有罪が決定していると言われる刑事裁判は非常に解りやすいが、民事裁判は当事者同士(代理人弁護士)の口頭弁論と準備書面だけで争う事になる為、この裁判の様に、弁護士の能力の差や、裁判官の能力、人間性によって全く逆の判決が出る事がある。これでは公平な裁判とは言えない。その為に再審請求や裁判官を審議する弾劾裁判があるが、これは請求自体が少なく、現状の裁判制度、特に裁判官の誤審を招くような制度と裁判官を擁護しすぎる制度の見直しを早急に行うべきだと痛感した》
《裁判官が合意書を無効としてしまった為に、株取引に関する全ての真実が一時的だが闇に消えてしまった。資金の出所についても、裁判官が返済金と認定した25億円、親和銀行他に支払った和解金、鈴木がA氏以外の債権者に支払った返済金、西に渡された裏金、そして何より鈴木が海外に隠匿した巨額な資金の行方、裁判官は審理の途中で合意書を無効にすることが出来るかどうか判断に迷ったのではないか。逆に迷いが無ければおかしい。しかし無効とする決断をしたことで他の重要な証拠を全て排除するしかなくなったために矛盾だらけの判決となったと思えてならない》
《再審されれば品田裁判長による一審の判決がいかに誤った内容であるか、証拠類を検証せぬ怠慢さ、支離滅裂な判断、高裁に至っては具体的な審理を行わず誤字脱字の修正のみに終始した判決を出したことで原審を丸呑みにする手抜き裁判の実態が浮き彫りとなるであろう。三審制を取っている日本の裁判制度がいかに名ばかりかが明白となり、制度そのものが機能していないことが分かる。これでは大谷直人最高裁長官が掲げる「身近な存在として国民からより信頼される裁判所」という標榜とは程遠い。今の裁判所の在り方を是正するに当たって最高裁長官としての大谷直人氏の真価が問われる》(以下次号)