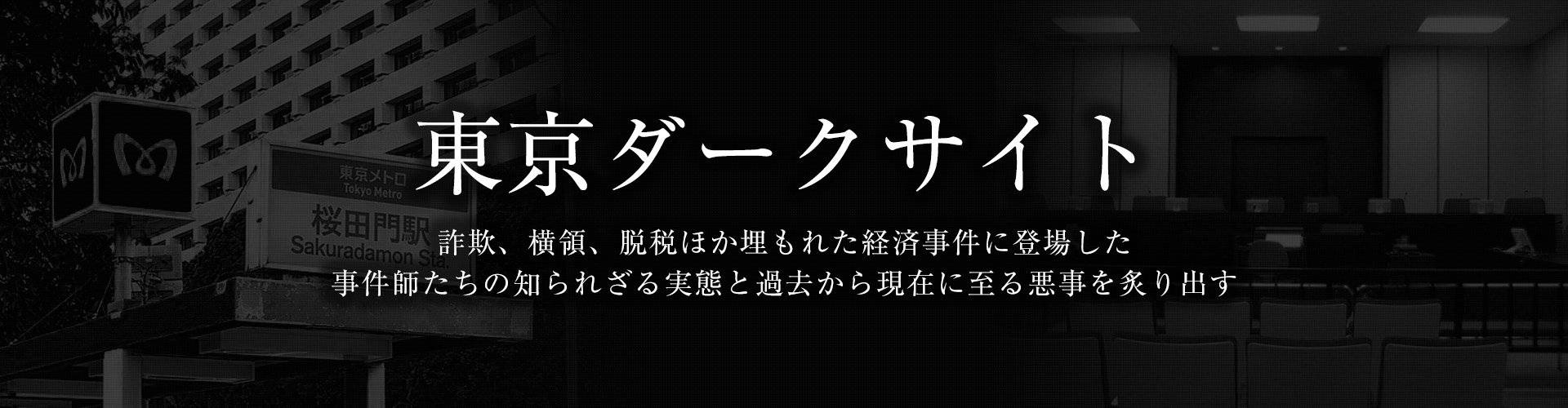《鈴木がA氏に送った手紙で和解協議を撤回し交渉を継続するとして、平林英昭弁護士と青田光市を代理人に指定して消息を不明にしてから、訴訟を起こすまでの約8年間、A氏の代理人は鈴木の住居を探索した。また、興信所にも依頼して鈴木の行方を追ったが、鈴木を見つけ出すことは出来なかった。そしてようやく代理人は、愛人のマンションに鈴木が住んでいる事を突き止め、メールBOXにメモを入れることもしたが、その後、青田が深く関係していた暴力団の組員に襲撃された。品田幸男裁判長はこの事件を無視しているが、A氏はかなりの費用をかけて鈴木の行方を捜している。交渉では平林と青田は全く話し合いを進展させず、月日だけが過ぎて行った。これも時間稼ぎをしてウヤムヤにしようとする鈴木の戦法だったに違いない》
《裁判官は、真実を追求して公正で正義ある裁きをするのが仕事だ。民事裁判において、真実を訴える原告を斜に見て自己の経験値だけで独断を下す裁判長など見た事も聞いたことも無い。裁判は法に照らして判断し、論理的にも説得力がなければならない。そして、その結論に信念が感じられる判決を下すべきだ。しかし、品田幸男裁判長にはその片鱗すら感じられない》
《弁護士の資格があれば、いろいろな資格が認められている。税理士や弁理士のほか、社会労務士や行政書士、海事補佐人等いくつもある。それを各監督官庁に登録すれば、これらの業務も出来る。このほか最近では、司法書士業務の代理も可能になったようだ。弁護士になれる人はこれだけの能力を兼ね備えている人だという事を国が認めているという事だ。逆に、これだけの資格を持っていれば、何でもできるという事になる。法律の裏も知っているわけだから、長谷川幸雄のような、強かな人間が悪用すればと考えると恐ろしい。長谷川が弁護士資格を返上したという事は、これらの資格も同時に失ったことになる。何故、鈴木の為にそこまで犠牲にするのか。やはり、それに見合う報酬を受け取っていなければ辻褄が合わない。その報酬も全て裏金だ。鈴木の事が世の中に晒されれば、それに連なった悪事の全てが露見する。これは稀に見る大事件として世の中を騒がせることは間違いない》
《世間を騒がせている鈴木の悪事を隠すために、代理人の長谷川幸雄弁護士は、日本の民事訴訟の欠陥を突いて全てが出鱈目な内容の証拠の捏造を謀り、原告のA氏を悪者に仕立てようとした。結果、それを支持した裁判官たちにも疑惑の目が注がれている。見返りは金銭だけでなく、裁判所内の人事にも関わることは想像に難くない。鈴木の悪事の全容が解明されたら、史上空前の裁判疑獄事件となるだろう》
《鈴木は、他人を信じさせる事に長けた恐ろしい犯罪疑惑者だ。不埒な弁護士や裁判官に守られて、今も獣の道を歩いているが、誰かがわずかに残っているはずの鈴木の良心に働きかけ、鈴木の心の中にある獣の心をへし折って改心させなければ、鈴木自身の命にも係わる事になると思う。何故ならば裁判所が鈴木の罪を容認してしまったからだ。法律で裁けなかった悪人を超法規的な方法で裁こうとする人間が現れる可能性がある。鈴木は、そういう処置をされても仕方のないほど酷い罪を重ねている》
《西は最後まで株の利益の1/3以上の分配金に固執したばっかりに、鈴木にいいように利用されていた。志村化工株の相場操縦事件に至っては、鈴木からの依頼で購入した志村化工株については後で全株を買い取るとの約束のもとに西に1000万株以上を買わせた一方で、鈴木は海外で手に入れた志村化工株約20億円分を売却し、裏で多額の利益を手にしていた。この件では西に相場操縦容疑がかかり東京地検特捜部に逮捕されたが、西は鈴木の関与を一切喋らず、西が全責任を被ることとなった。このように西は株取引の利益の1/3以上をもらうという鈴木との密約の実行を信じて鈴木の思うがままに操られ、鈴木の蟻地獄から抜け出せない状況に陥ったのだ》(関係者より)
《鈴木は株取引を行うに当たって、A氏から安定的に買い支え資金の支援が約束されれば、億単位の利益は間違いないと踏んでいたはずだ。そこで問題となるのが株取引の名義人であり、ペーパーカンパニーにすることで自身の関与を消す対策を講じたのだった。利益の海外流出も、香港を窓口にして海外に拠点を持つペーパーカンパニー名義で行えば誤魔化しがききやすい。銘柄ごとに10億円単位の利益金が海外に隠匿されることになったが、実際の利益獲得の現場は東京だったのだ》
《人間は予定していれば、いくらでも演技をするが、不意を突かれた時は困惑して言い訳をする。鈴木の言動はこの繰り返しだ。そして、その時の言い訳は全てが嘘なのだ。こんな厄介な奴はいないが、1000億円以上とみられる隠匿資金を守るためには鈴木にとって嘘をつくのは何でもない事なのだろう。良心や感謝という言葉はこの悪党には通用しない。鈴木は自分の身に本当の危険が迫らなければ真実を話すことがないのかもしれない》(以下次号)