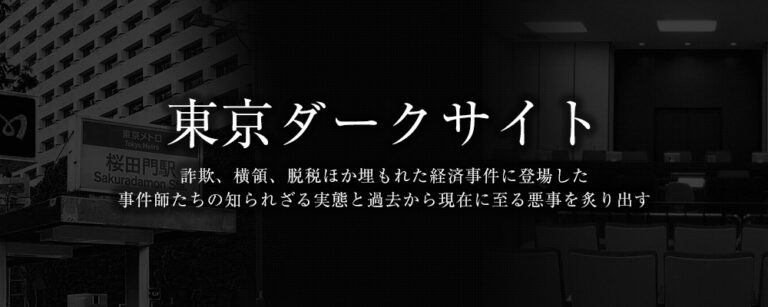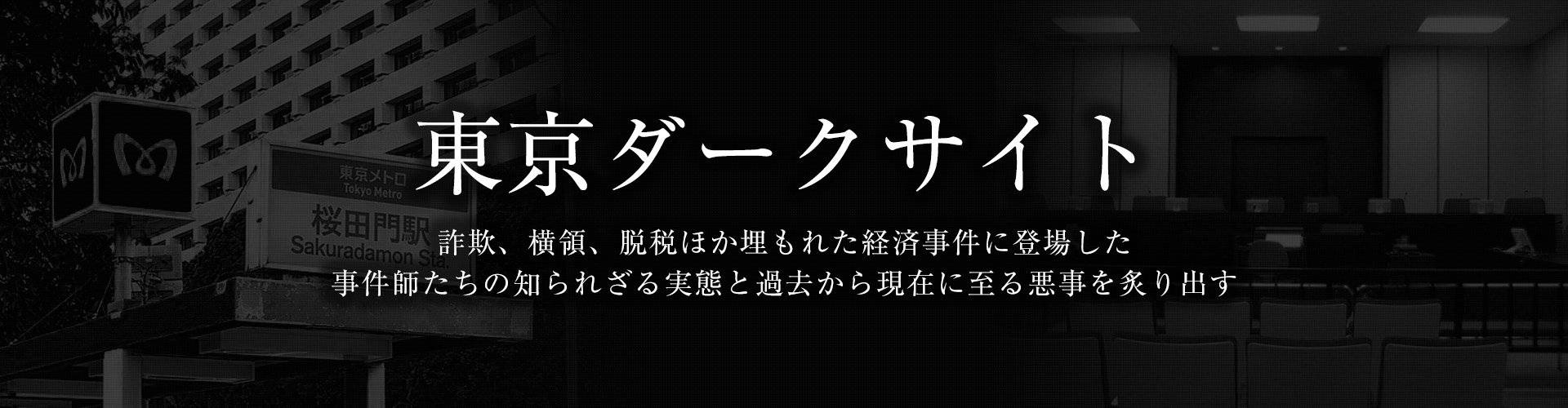《紀井氏はA氏と西、鈴木の間で交わされた合意書の存在は知らずに、鈴木に「儲け折半」で誘われて株取引を手伝う事になった。鈴木の指示を受けて高値で売却を繰り返していた紀井氏の仕事場のマンションには、1箱に3億円の札束が入ったダンボール箱が積み上げられていたという。紀井氏のその頃の報酬は年間で6000万円ぐらいだったようで、一般サラリーマンに比べれば10倍近かったようだが、鈴木と約束した額とはひどくかけ離れていた。株取引の収支を誰にも明かさず、誤魔化し続けた鈴木の剛欲さと悪辣さがよく分かる》
《品田裁判長の独断裁定には呆れる、というより、こんなことが法廷で起こってはならないという怒りが湧く。鈴木の債務返済金について、品田裁判長の事実認定は誰の供述とも一致せず、品田裁判長が自分勝手に筋書きを作って判定したのである。到底納得できるものではない。こんな裁判はあり得ない》(関係者より)
《日本の株式市場は、日本人だけの投資家で株価が動いているわけではない。海外の機関投資家が莫大な資金を投入して株価を操作している場合が多いからだ。その中には、鈴木の様に海外に設立したペーパーカンパニー名義で外国企業を装って売買を繰り返している日本人投資家も多い。日本の金商法(旧証券取引法)や外為法はザルのように抜け穴が多く、売買利益金は海外の非課税地域に送金され、日本の税法を逃れている。タックスヘイヴンと呼ばれる非課税地域は世界各所にあり、覚醒剤の密売や兵器密売の宝庫となっていて、隠匿資金は世界的なテロ組織の資金源になっていると言われている。世界各国の司法機関の取締りは強化されているが、日本は一歩も二歩も立ち遅れていて鈴木のような悪党を野放し状態にしている》
《裁判で、再審の開始が決定されるという事は、手掛けている弁護士にとって最高の喜びで名誉らしい。弁護士界の名士としても扱われるようになり、依頼人も激増することになる。「開かずの扉」をこじ開けるという事はそれだけ難しい事だという証明だが、可能性が低い事は弁護士が一番よく知っている。裁判所のハードルを突破するには相当の苦労と努力が必要になる筈だ。この様ないびつな制度が何時までも蔓延っていいのだろうか。裁判官達は不落の堅城に身分を守られているようなもので、こんな不公正不公平な事があってはならないはずだ》
《品田裁判長は「合意書」に基づく株取引を、理由をこじ付けてでも否定した。何が何でも裁判の争点から株取引に関する事案を排除したかったのだろう。品田裁判長は経済情勢すら理解に乏しかったと思われるが、否定する理由に株取引の銘柄が特定されてない事を取り上げた。しかし、それが裏目に出てしまった。株式市場は相場が目まぐるしく変化している。そんな中で先々の銘柄の特定など出来る訳がない。道理にも実態にも合わない判断は裁判官として支離滅裂で全く無能と言うしかない》
《裁判では、品田裁判長の独断により株取引に関する事案が闇に葬られたと言っても過言ではないだろう。当然、鈴木が手にした利益の470億円は表沙汰にならなかった。脱税の疑いが濃厚であるにも拘らず、品田裁判長が一切触れようとしなかったのは、隠匿先が海外のタックスヘイヴンである事が関係しているのだろうか》
《鈴木は志村化工株の事件で西に判決が出るまでは仮面をかぶっていた。西の有罪判決が出た途端に鈴木の言動が豹変した。これは鈴木の常套手段だった。さすがに西も我慢できなくなったが、約束の配当を受け取るまではと耐えたようだ。しかし、それが自分の命を縮める事になってしまったのではないか》
《裁判所という組織は最高裁判所事務総局の人事権によって個々の裁判官を支配し恐怖の坩堝に堕としているという。そうであれば、裁判官ばかりを責めるのは気の毒だが、この裁判で一番被害者となるのは訴訟を提起した原告であるという事を裁判所は全く理解していない。困って裁判の裁定に縋っている国民はどうすればいいのか。裁判所や裁判官が今のままであれば、自分達で解決しようとして国のあちらこちらで争いが起こり、力のある人間が勝利者となるような事態が起きる》(以下次号)