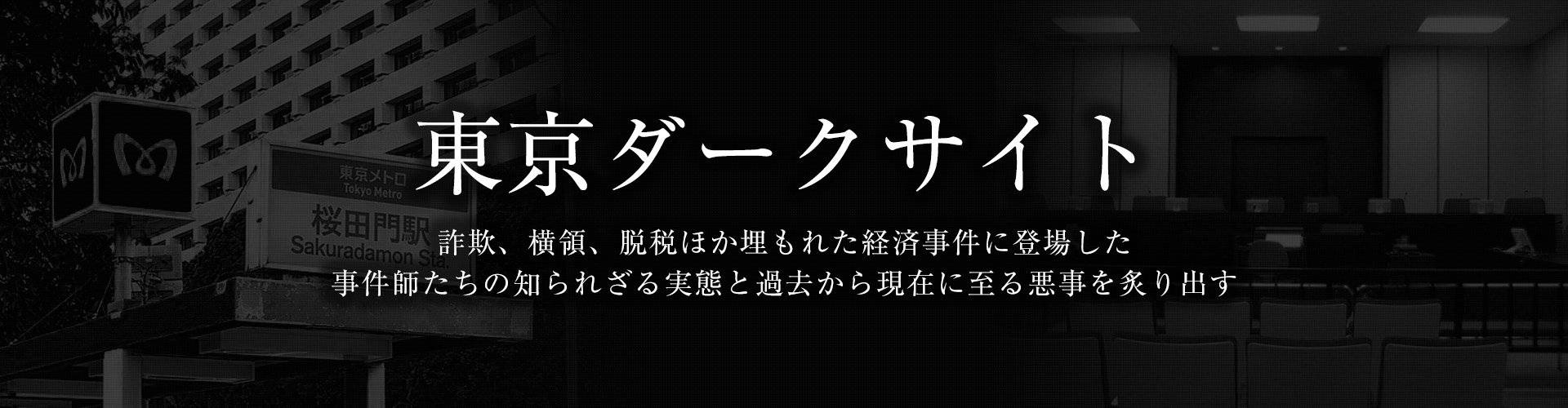《裁判所組織の腐敗や裁判官の不正について、大手マスコミは権力に平伏し全くといっていいほど報道しない。不甲斐ないマスコミに代わって、最近では退官したエリート裁判官たちが書いた本が話題になり、裁判所組織の腐敗と裁判官の不正が批判されるようになった。マスコミが裁判所に忖度し本来の役割を果たさない理由が分からない》
《鈴木は全ての面でやることが悪質だ。借金の返済でも「今なら借りてでも返せるが、この先は分からない」と言って金額を1/10や1/20に減らすが、債権者も回収できないよりましだと思い、大損しても諦めるようだ。タカラブネ株を山内興産から預かった時も、西に市場でほんの一部の株を売買をさせて高値売却を装い、残る大半の株は売ってしまって自分と会社の資金繰りに充てていた。清算しなければいけなくなったら、「市場での売買で損失を出してしまった」と言って逃げる積りだったというから、明らかな詐欺行為だろう。A氏に対する騙しと裏切りはあまりにひどすぎて、西まで自殺に追い込んでおきながら、裁判では西が死亡していることを悪用してA氏が暴力団と密接な関係にあるというでたらめな証言を「西が言っていた」等と繰り返し誹謗中傷した。それを言うなら、鈴木や青田の方がよほど暴力団を使って悪事を働いているではないか》
《鈴木は用心深い悪党だ。和解協議で70億円の支払いを約束したが、香港に隠している利益金の事が気になり、和解協議の1週間後に1人でA氏の会社を訪問して和解金支払いの打ち合わせをする振りをしながらA氏の様子を観察していたに違いない。この時の鈴木はA氏を安心させる効果を狙って、殊勝な態度でA氏に接していたように思う。鈴木はA氏が不信感を持っていない事を確信したようだが、約1か月後にA氏に手紙を送り付け、西と紀井氏を裏切り者扱いにして和解協議での約束を一方的に留保撤回してしまった。その後の交渉の代理人に就いた青田光市と平林英昭が鈴木を唆したとみられている》
《鈴木の裁判での一番の大誤審は、株取引の証となる「合意書」契約の有効性が認められなかった事だろう。品田幸男裁判長が「合意書」契約を否定したことにより、株取引関する事案は全て裁判の争点から消えることになる。被告側の長谷川幸雄弁護士にとってそれが最大の課題であったはずだ。しかし法に携わる人間であれば、民法で定められた「契約自由の原則」を知らない訳がない。これを無視して裁定を下した品田裁判長は、とんでもない過ちを犯したと言わざるを得ない》
《鈴木が裁判に提出した物的証拠は平成11年9月30日付の確認証しかない。A氏側にはFR社の常務だった天野裕氏の証言、株の売却を専従した紀井氏の陳述書の他、西が鈴木の代理として書いた書類の数々、A氏を心配する知人や友人の陳述書があった。A氏の代理人中本弁護士が法廷に提出していないものも複数あったらしいが、提出されている証拠書類だけでも鈴木の嘘を証明するのに充分であった。しかし、裁判官たちはA氏側の証拠を悉く無視した。A氏側の主張を排除したうえでの判決は明らかに誤判としか言いようがない》
《品田幸男裁判長は「勧善懲悪」という言葉を実践したことはないのか。この裁判は全く逆の判決を下している。裁判長としてのモラルが全く感じられない。罪悪感を鈴木と分かち合うべき所業だと思う。品田裁判長のA氏への心証はどのようなものだったのだろうか。民事裁判は裁判官の心証が大きく左右するとも言われるが。真実から目を背けてはならない。面倒な事には一切関わりたくないという精神では裁判官は務まらない》
《鈴木と共謀しA氏を騙していた西は、株取引で得た利益の授受のために香港へ向かったが、鈴木の罠に嵌り殺されそうになる。一命を取り留めた西は、和解協議の場で鈴木の裏切りを告発するが、もし万が一香港で死んでいたら真実は闇の中に埋もれてしまっていただろう。その後、鈴木と青田に追い詰められ自殺したが、死ぬ覚悟があれば、生きてA氏のために協力するべきだったと思う》
《合意書の破棄や宝林株の利益分配等で40億円という金を西は鈴木から受け取っていたというが、西も相当にあくどい。鈴木を紹介するまでにA氏から116億円という借金をして自分や会社の資金繰りに充てて、何から何まで世話になっておいてA氏をよく裏切れたものだ。出世払いくらいの感覚でA氏の金に寄生したのだろうが、そうであれば株取引の元になる合意書の作成を提案した人間の責任として、株取引の収支は明確にさせておかなければならなかったはずだ。それを「社長に返済したら、自分たちの手元には何も残らない」という鈴木の言葉に乗り、簡単にA氏に嘘を重ねるようになった。それも鈴木を庇うことばかりで、いずれは鈴木とともに責任を負わされるというリスクを西は持たなかったのか。志村化工株の事件、香港で利益分配を受け損なって殺されそうになった事件、そして最終的には自殺に至る成り行きを、西は株取引を開始した直後からA氏を裏切った時点ですでに感じ取っていたのではないか》(以下次号)