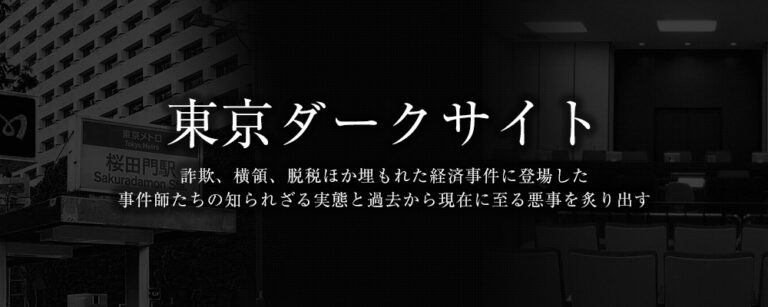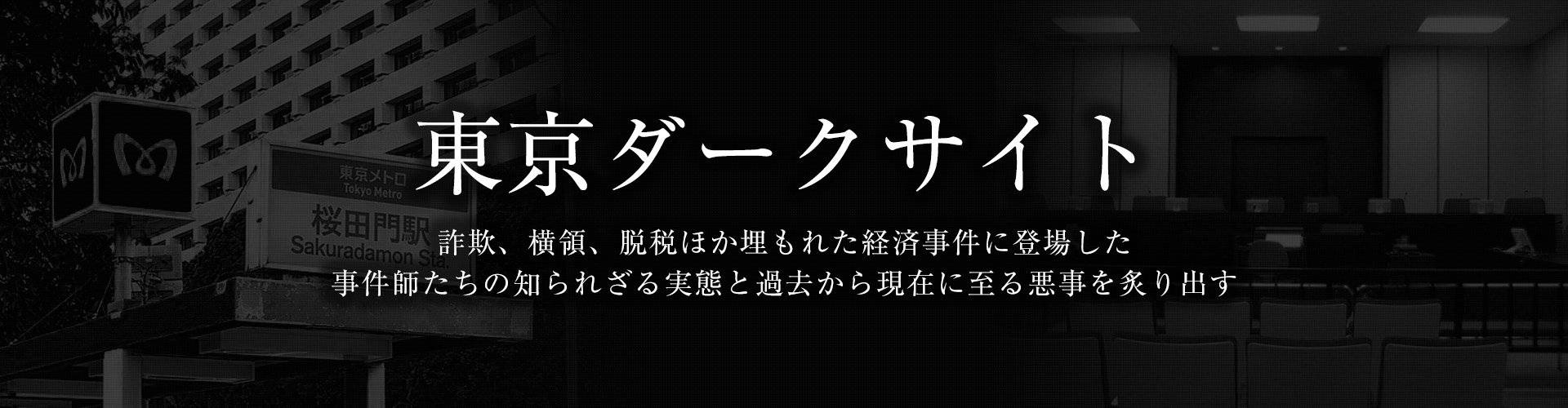《鈴木は、自分の代理人弁護士と話をしている時は「自分が被害者だ」とでも言っていたのだろうか。良識がある筈の弁護士が、どこまでも鈴木を庇うのは考えられないが、やはり法外な報酬の為なのか。弁護士達は、鈴木の金は脱税した裏金だと知っていた筈だ。鈴木には領収書が不要だったから、弁護士達も弁護士事務所も申告しなかった可能性は高い。弁護士に裏金を払っている法人や個人がいても不思議ではないが、税務署はしっかりマークして摘発するべきだ》
《品田裁判長は、貸付金返還請求の部分では鈴木の嘘に翻弄されず、比較的冷静な判断を下していたように思う。ただし、25億円の返済額、返済方法、返済時期に関しては強引な辻褄合わせをしている。しかし、株取扱合意書を始めとする検証以降は、余りにも無知識から法に照らすことを忘れ、経験則と倫理則だけでの判断で暴走してしまった。合意書は法に照らせば問題無く有効と判断できる契約書であったにもかかわらず、無効にしてしまった。そこには裁判所の意向と指示があったのではないだろうか。そうでなければ裏取引があったことを疑わざるを得ない》
《鈴木はA氏から現金で融資を受けていたが、それでも資金が不足する事があった。そんな時には宝石類や高額な絵画を持ち込んで購入して貰っていたようだ。その中には2キャラットのピンクダイヤとボナール作の絵画があった。その2点で3億円だったが、A氏は価格交渉もせず言い値で買ってあげた。しかし、鈴木は絵画を一度もA氏に持参しなかった。購入時から別の債権者に担保に入れていたことが後に判明した。他にも上代が40億円の時計を4億円で預かり、この金も一切払っていない。これもFRではなく鈴木個人である。これらは詐欺師の常套手段であったが、A氏は鈴木には催促をしなかったようだが、このような鷹揚なところもあったようだ。鈴木はこんなA氏の隙に付け込んだのだと思う》
《西が評価していた鈴木の器量とは、人を騙すノウハウが長けているということだけではないか。そんな鈴木を西は何故A氏に紹介したのか。平成9年8月頃、エフアール社は経営破綻が目に見えており、鈴木個人は10日で1割以上の金利でも融資を受けられないほどで、西もまた連帯保証をして20億円前後の資金調達に協力していたが、それも限界にきて、鈴木自身は自己破産や自殺さえ頭をよぎっていた。西はA氏に鈴木への融資を依頼する際にも鈴木の実情を語っており、「エフアールは経営状態がめちゃくちゃですが、鈴木は有能です。何とか力を貸してやってください」とA氏に懇願していた。そんな話を聞けば、誰も鈴木には貸さないが、A氏は快く貸した。鈴木は和解後にA氏に送った2通の手紙に「大変世話になった」とか「男として一目も二目も置く男に会ったことが無い」と書いているのに、なぜA氏をとことんまで裏切るようなことをしたのか。和解協議の場で強迫され和解書に署名したのは心裡留保に当たるとも主張したが、株取引の利益を独り占めにして、それがバレたから和解協議になったのだろう。鈴木が被害者面するのはおこがましい》
《民事裁判は弁護士の戦術によって有利にも不利にもなるようだ。鈴木の代理人弁護士の長谷川は裁判戦術に長けていたように思うが、この裁判の様に裁判官を味方につけることが一番の戦術だと思う。品田裁判長は長谷川に篭絡されてしまったのか。これは公正公平な裁判ではない。再審をして真実の裁きをするべきだ》
《A氏の人徳は、三重県の実家が「仏」と呼ばれる屋号を持ち、困った人達の救済を惜しまなかった家系からくるものだろう。人を信じ易く助けを求められると損得勘定抜きに協力する性格だけに、鈴木のような詐欺師に狙われやすい。そんなA氏を騙した鈴木は、当然バチが当たるはずだ》(関係者より)
《人は第一印象で光が差していたり、影が見えたりすると言われるが、裁判官たちの鈴木の第一印象はどうだったのだろうか。鈴木は多分、A氏を見て「ただ者ではないオーラ」を感じていただろう。そのために裏切りが発覚しないよう、西の陰に隠れるようにして直接A氏と会わないようにしていたのだと思う。後ろめたさがあって、自分の魂胆を見抜かれないように用心していたのだ。鈴木の悪事は、この用心深さが支えていると思う。A氏の協力で宝林株の購入が決まった時の用心深さと用意周到さが鈴木の今日につながったと言っても過言ではない。秘密厳守には極めて敏感で、仲間同士であっても情報交換を許さなかった。その為に側近の人間からも信頼されることが無かったようだ。今後はその事が仇になり、莫大な隠匿資産の管理が1人では困難になる。金銭に強かな人間が多い海外の投資業界で隠匿している資産を護りきる事は至難の業のはずだ》
《裁判に関わる記事をここまで注目するのは初めてだが、日本の裁判はこんなにも善悪の見極めができないのかと情けなく思った。日本は法治国家であり、裁判官は全ての裁判で公平公正の実現を図るものと当たり前のように思っていたのに、心底裏切られた気持ちが強い。裁判官も人間であるから判断ミスや、裁判官によっては解釈の違いがあるとしても、この事件の勝敗の付け方は酷すぎる。そして裁判所の裏側で何が行われているか分からないが、裁判所という組織に属する人達への信頼が損なわれたのは確かで、民事においても速やかに裁判員制度を採用するべきと思う》(以下次号)