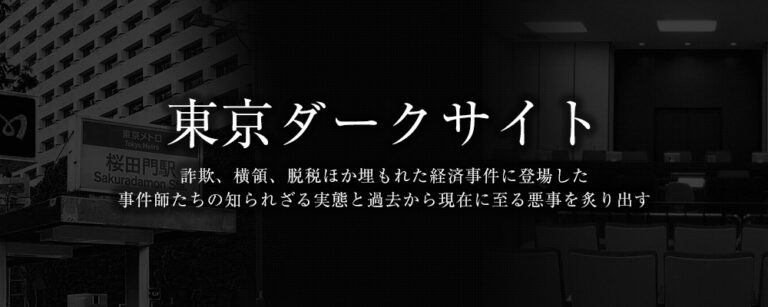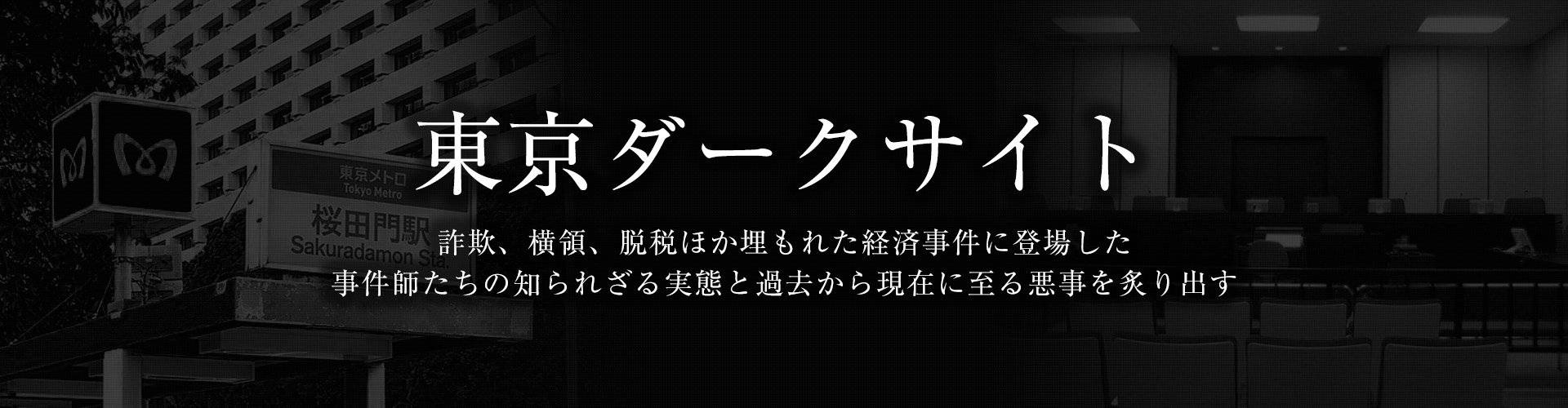《詐欺師と同様に曖昧な発言ばかりしているのが政治家だ。特に時の権力者たちの責任は曖昧な処理で済まされている事が多い。一方で、物事の黒白を明確にするのが裁判所だ。三権を分立させている意味がそこにもある筈だ。しかし、実際は「三権同立」状態になっている。裁判所が組織の腐敗によって立法府や行政府の権力に伏している。忖度を繰り返し、公正な裁判さえできなくなっている》
《鈴木は、余裕がある時は高圧的な言動をするが、和解協議の様に追い詰められた時はその場を凌ぐ術を駆使する。自分の非を認めて善人の振りをして甘い約束をして他人を騙す。西は和解協議の場では激しく鈴木と口論していたようだが、その1週間後の鈴木とA氏の面談には同席していない。鈴木との間に密約でも交わしていたのだろうか。香港の事件も中途半端に終わっている事にも疑念が湧く》
《日本の裁判制度は国内に留まらず諸外国から批判されている。日本は三審制と3人の裁判官の合議制が定められているが、どちらも建前だけで正常に機能していない。裁判所組織自体が明治時代からの悪しき慣習を改めようとせず、上意下達と情実人事が蔓延り、将来ある優秀な裁判官の育成を阻んでいる。自己の出世だけを目標にして日々の職務を無事果たす事だけを考えている人間が他人の善悪を平等に裁くことは不可能だろう》
《裁判では裁判官が絶対的権限を持っている。その中でも裁判長が絶対である。その裁判長と相手方の弁護士が手を握れば、到底勝ち目はない。今回の鈴木の裁判は、そんな絶対的不利な状況下で判決が下されたとも考えられる。品田裁判長も裏で高額な金を積まれたら手が伸びないとは限らないとする推測もあるが、。鈴木には金がある。裁判の勝訴を金で買おうとしてもおかしくはない。いや、鈴木が金で買おうとしない訳はない》
《弁護士は、依頼人を有利にするために法廷での戦術を練る。事件の裏側にある事情も把握しなければならない。法廷では最初の一歩が大事という。特に民事裁判では、裁判官や相手方弁護士との駆け引きが勝敗を分ける場合が多い。裁判官や相手方弁護士の過去の実績や性格、癖等を知る事も大事だと思う。A氏の代理人であった中本、戸塚の両弁護士は裁判前の準備があまりにも不足していたのではないか。訴訟内容がA氏に有利で勝訴できる可能性が高かったと想定した為に油断していたのだと思う。そうでなければこんな結果にはならなかった》
《裁判官を33年間務めた瀬木比呂志氏が知られざる裁判所の実態を告発した「絶望の裁判所」によれば、現在の裁判所は、最高裁幹部による、思想統制が徹底され良識者を排除し、腐敗まみれだという。裁判官の買収も横行しているのであれば、今回鈴木の無理筋な不当判決も合点がいく。瀬木氏曰く、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは絶望だけだという》
《鈴木が海外に1000億円超の巨額な資産を隠匿しているという話は驚くべきことだ。鈴木のペーパーカンパニーの常任代理人を務めて来た杉原弁護士は現在も業務や管理の情報を握っているはずだ。同時に脱税にも大きく加担している事になる。現役の弁護士が資産隠しと脱税に関与している事実を踏まえて、第一東京弁護士会は杉原弁護士と平林弁護士の処分をどう考えているのか。協議内容や処分を早々に公表するべきだろう。杉原弁護士の行為は犯罪である。ウヤムヤな結果は許されない》
《自分の周囲を見渡しても、このサイトを読んだ人は異口同音に鈴木という人間を非難し、日本の民事裁判の制度の曖昧さと裁判官の能力の低さに驚き、司法機関の腐敗を嘆いている。これは大きな社会問題だと思う。A氏と鈴木の問題をきっかけにして、悪しき制度を改めるべきだと思う。マスコミも各役所とのしがらみを捨てて正義のペンを振るうべきだ》(以下次号)