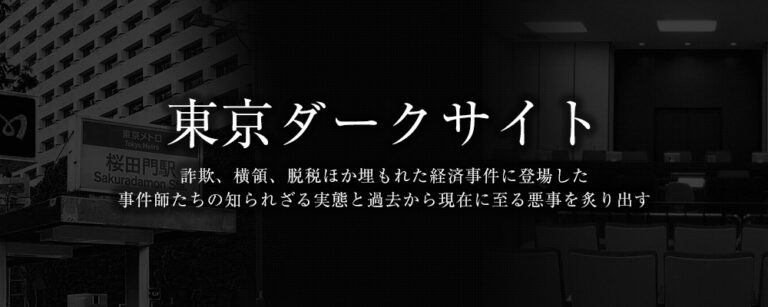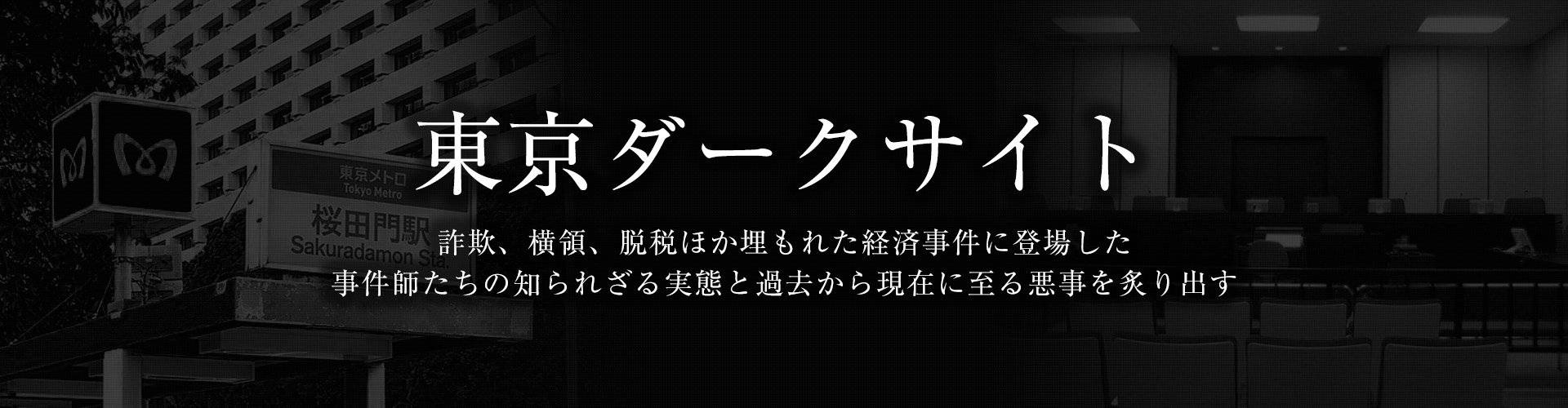《冤罪や誤審は二重の不正義だと言われる。刑事事件の場合は無実の人間を処罰し、真犯人を取り逃がすことになる。民事裁判は加害者が得をし、被害者が損をすることになる。刑事事件の場合は人命に関わる事もある。民事事件の場合は犯罪が繰り返されることになり、被害者が増えることになる。それでも裁判官には罰則がない。冤罪で死刑判決を下し、死刑が執行された後に無実が判明する場合がある。この場合、捜査した警察、起訴した検察は世間から厳しい批判を受けるが、裁判官が責任を追及されたとは聞かない。まして民事裁判においては裁判官の誤審誤判についての報道は全く聞かない。出世街道からは外れるかもしれないが、退官までの身分は保証されるようだ。わが国には「裁判官保護法」という法律があるのか》
《日本の裁判制度は三審制を掲げているが、鈴木の裁判では高裁がほぼ一審判決を踏襲し、誤字脱字の修正に終始して、高裁としての独自審議を怠ったことが明らかだ。野山裁判長の明らかな手抜きだった。この結審に納得出来る者がいるはずがない》
《鈴木の事は、多くの情報サイトや動画の公開によってかなり拡散していることが分かる。鈴木本人はもとより、家族の事もかなり詳しく掲載されている。多くの読者の投稿文を読んでも、当然ながら鈴木と取り巻きへの批判は非常に厳しい。しかし、鈴木の言い分は多くの証拠によりほぼ100%虚偽が明らかにされたことで、鈴木は沈黙せざるを得ないのだろう。嵐が過ぎるのを待っている積りかもしれないが、この問題は風化するどころか益々世間から注目を浴びることになる。鈴木が被害者に詫びを入れて、約束した事を履行しなければ司直の手に委ねられることになる。今後は民事事件だけではなく刑事事件で告発され、世間を大いに騒がせることになるのはほぼ間違いない》
《裁判所と検察庁には人事交流というのがあって、お互いの知識を高め合うために、検事が裁判官に転任し、裁判官が検事に転任する事があったという。この件の長所、短所については国会で論議された事もあるが結論は出ていない様だ。検察はその時の政権と緊張感を持って接している印象を持っていたが、表裏一体で長期政権が続くことで黒川元検事長のように政権が検察庁の人事に介入するというルール破りが起こる。三権分立と言われているが、行政と司法の境界が崩れている様では裁判所組織の腐敗も仕方のない事なのか。これでは国民の安全と安心は守られない》
《A氏の代理人の中本弁護士は「質問と回答書」(乙59号証)が法廷に提出されたことをA氏には詳しく話していなかったようだ。それでよく代理人が務まったものだ。A氏が乙59号証の内容を精査していたら、即刻反論したはずだ。中本弁護士の後手、後手の対応は完全に裁判の行方を狂わせてしまった。取り返しがつかないことをしたのは間違いない。A氏と中本弁護士が鈴木と青田から名誉毀損で訴えられたが、A氏はすぐに反論して回答したのに、中本弁護士が6か月以上も裁判所に提出しなかったので、強い口調で抗議したために中本弁護士がすぐに提出すると、A氏への訴えはすぐに棄却されたという。中本弁護士には代理人としての自覚が無さすぎたのではないか》
《裁判所は仮にも日本の三権の一角を担う国家機関である。その裁判所には被告側と利害関係を築いて職権を濫用して勝訴判決を下したり、私服を肥やす為に利用する裁判官が存在するとまで疑われている。そんな獅子身中の虫を排除出来るような、自浄作用が今の裁判所には全く働かない。裁判所がこんな有り様では日本の将来までもが危ぶまれる》
《鈴木は裁判で、A氏に脅かされて「和解書」にサインしたかのように和解協議での様子を主張し、「合意書とか和解書とは関係なく、今まで稼いだ資金の全部50億円をやるから、これで解放してくれ」と言って、和解書の内容も全く見ず確認もしなかったと証言しているが、鈴木本人が「合意書」の約束を破り裏切った行為を認め、内容も何度も確認してA氏と西にそれぞれ25億円を払うとして和解書に署名指印したのではないのか。さらに「私の男気を見ていて下さい」と言いながらA氏に2年以内に20億円を支払うことも約束して交わした契約であったはずだ。これが鈴木の見せたい男気か》
《鈴木は宝林株の取引で予想外の利益を生む事が出来たおかげで、その巨額の利益から親和銀行に和解金の約17億円を支払うことができて実刑を免れた。A氏との出会いがなければ株取引で多額の利益金を手にする事が出来なかったから、当然、和解金の約17億円も払えず懲役3年の有罪判決に執行猶予はつかなかった。そのことだけでも鈴木にとってA氏は救世主的存在であることをもう一度振り返って考えてみることだ。保釈直後に西が毎日のように鈴木を訪ねた時、鈴木は朝から飲んだくれて自暴自棄になっていたというではないか。しかも、西に宝林株800万株の買取話が持ち込まれたから再起のチャンスが巡ってきたが、その宝林株の買取資金3億円を出したのも、その後株取引で買い支え資金約58億円超(総額では207億円)を出したのもA氏だった。それもこれもなかったことになれば、鈴木は一体どういう事になっていたか分かっているはずだ》(以下次号)