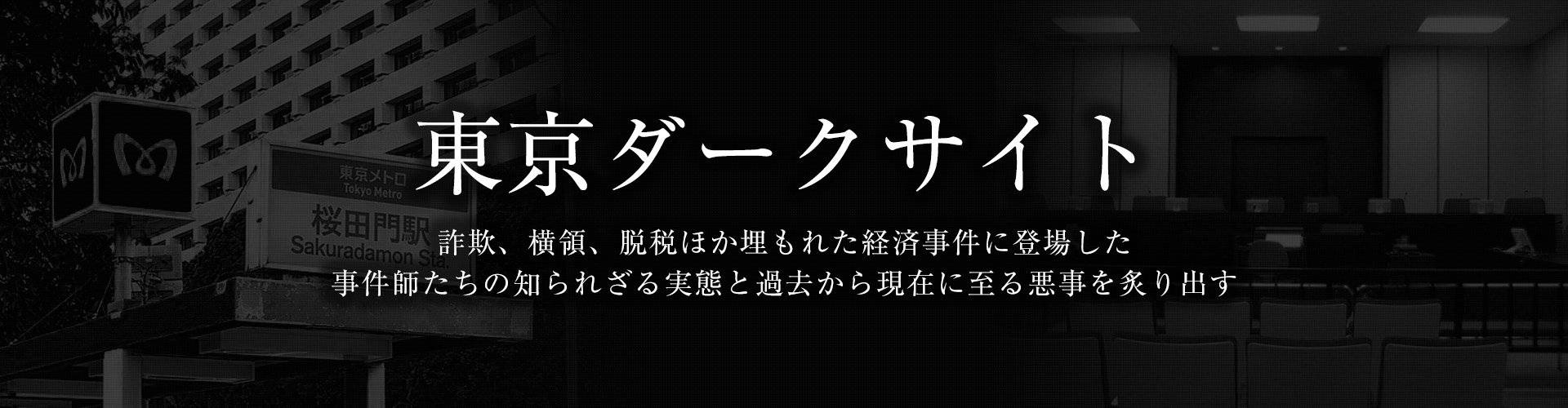《鈴木は西の紹介でA氏に会い、西の協力もあってA氏から資金を援助してもらう事に成功した。担保は無く、保証人は西だけだった。倒産寸前で担保価値のないFRの手形を借用書代わりに預けるだけの条件で融資を受けた。しかもA氏の温情で、預けた手形は返済期日の3日前までに現金を持参することを約して、「銀行から取り立てない」という事もA氏に了承して貰っていた。常識では考えられない条件だった。鈴木は、親和銀行事件で逮捕される日を想定しながら西を通じてA氏から融資を受け続けた。そして、逮捕される3日前にA氏を単独で訪れ、現金8000万円とピンクダイヤを販売委託として、それに一度も持参していない絵画を合わせて合計3.4億円で借り出したのだった。鈴木は恐らく、この日で逮捕拘留中の資金繰りにメドを付けたと思われる。それを証拠にFRは鈴木が逮捕拘留されても倒産しなかった。しかし、驚くことに鈴木は最初の借入金も含めてA氏に一銭の返済もしていなかった。この時点でのA氏の鈴木に対する貸付金は元金で約28億円に達していた。A氏の温情や器量の大きさというものを超越した金額だったのではないだろうか》(関係者より)
《西は、鈴木の目論見に協力することにより、自分の資金難も切り抜けたと思う。西はある意味、鈴木より根性の腐った人間だ。バブル崩壊以降、長年にわたって面倒を見てもらい、周囲の人が不思議がるほど可愛がってもらっていながらA氏を裏切る行為は万死に値するが、息子の内河陽一郎は父親に輪をかけるほど人間として最低の男との声も少なくない》(関係者より)
《鈴木は奪った金を海外で運用して、1000億円以上にもなっていると言われているが、A氏に返すべき金を返しても十分な金は残るはずだ。返す金があるのであれば解決する事に尽力するのは当たり前ではないか。このままでは蟻地獄から抜け出す事は出来ない》
《鈴木にとってA氏の温情は「猫にカツオブシ」「馬に人参」「盗人に負い銭」状態だったことだろう。そんなA氏の好意を裏切る奴は絶対に許せない。この悪党は感謝、恥心、義理、人情、真実、礼儀といった人間として最低の道徳さえ知らない外道だと言える。外道には法に則った罰は必要ない。このまま悪事を通すなら超法規的な「天誅」を与えるべきだ。人間としての扱いは無用だと思う。裁判所がそれを認めなくても社会は容認するべきだ》
《鈴木のような極悪人を放置するのは、国を司る裁判所の重大な責任だと思う。裁判所は三権分立の中で立法府にも行政府にも干渉されず、独立した聖域として国民から信頼されてきたはずだが、その聖域に棲む役人の実態は国民を蔑ろにして、自己の保身ばかりに奔り、特権を駆使し、建前ばかりを振りかざす魑魅魍魎ばかりだ。裁判所組織には不正と矛盾ばかりで「正義」は無い》
《裁判官に対する被告側との癒着の疑惑が拭えない鈴木の裁判は、YouTubeの拡散もあってか、波紋は広がるばかりだ。法律の専門家で無くても、品田裁判長の裁定には疑問を抱かざるを得ない。根拠も無しに被告側の主張を一方的に採用して勝訴判決を与えた背景には、被告側の長谷川弁護士を通じて品田裁判長との裏取引が指摘されている。これが事実であれば裁判所の崩壊につながる大問題だ》
《鈴木は、西を通じて、A氏に借入金の減額を願い出て、株の配当が増えることをチラつかせながら交渉した。しかし、減額交渉に成功しても株の配当金を支払ったことが無い大嘘付きだ。A氏は平成14年6月に、鈴木との貸借関係を整理するために、西と鈴木を会社に呼んだ。数日前に西から「今後は株の配当金が大きくなるので、鈴木に対する債権を25億円にしてやってくれませんか」という依頼があった。A氏は「株の配当金が増えるなら」と貸付金を25憶円に減額して、新たに借用書を交わそうと考えた。しかし、当日に鈴木は「西さんに社長への返済金の一部として10億円を渡しています」と言い出した。A氏が驚いて西に確認すると、西は突然の話に狼狽しながら心当たりがあるようで、この鈴木の言葉を容認した。A氏は、この時鈴木に「何故そんな大事な事を連絡してこないのか」と叱った。鈴木は「すみません」と詫びただけだった》(関係者より)
《世間では、普通の人間はある程度の地位や名誉、そして財力を得れば満足するものだと思うし、そこまで届かなくても人の物を盗むことはしない。それでも良き家族や友人に囲まれて人生を送る事が一番の幸せではないか。鈴木は、最終的にどんな人生を目指していたのだろうか。こんな悪党が幸せな人生を送る事は世間が赦すはずがない。何時までも自分の都合の良いように世の中が回る事はあり得ない。このままでは鈴木のこれからの人生は不幸の連続になる。そうでなければ鈴木という悪党の人生の辻褄が合わない》
《長谷川元弁護士への批判が止まないようだ。当然だろう。裁判で「質問と回答書」(乙59号証)という中身が全てでっち上げの陳述書を使って、原告を誹謗中傷した罪は、例え弁護士を辞めても消えない。長谷川は弁護士であるにも拘らず、超えてはならない一線を超えてしまった。後悔先に立たずで、いくら金の為とはいえ、よく熟考するべきだった》(以下次号)