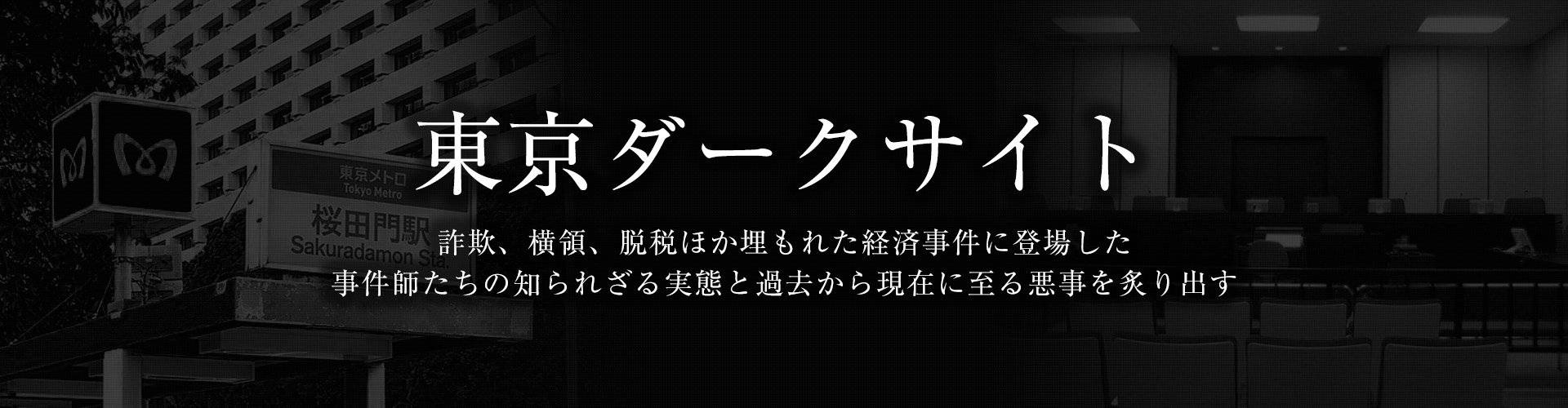品田幸男裁判長は、何故、合意書と和解書を無効にしたのか。A氏側が提出した多くの証拠類が、鈴木と西が合意書に基いて株取引を実行していた事実を裏付けていたことは明らかだった。しかし、品田は株取引に係る証拠類を排除、もしくは軽視した。それは判決に反映されていなかったことですぐにも分かることだった。品田が証拠類を排除したのは、強引に合意書を無効にするために故意にやったことではないか、という疑問が湧くのは当然だった。
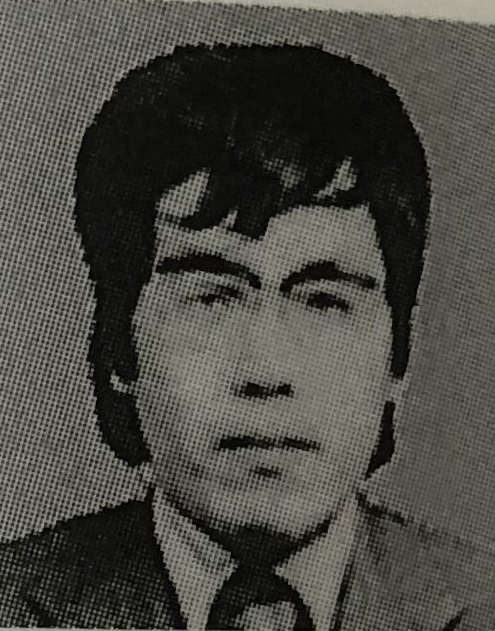
(写真:長谷川幸雄。元弁護士。金のために最悪の弁護活動をした。鈴木の犯罪疑惑を隠蔽した責任はあまりに大きい)
株取引が実行された事実を明示する重要な証拠として挙げられる合意書と和解書について触れる。
品田裁判長は判決で「合意書」に基づいて鈴木と西が株取引を実行した痕跡がみられず、何よりも平成18年に「和解書」が作成されるまでの7年間に株取引に係る三者の協議が行われたという具体的な証拠も提出されていない、と言って「合意書」の有効性や実行性を否定した。しかし、法廷に提出された多くの証拠書類を精査すれば、鈴木が故意にA氏に会おうとせずに西をうまく利用して逃げ回っていたことがすぐにも判明したはずだ。それで、裁判官が鈴木の主張の全てが虚偽ではないか、という疑念を持たない方がおかしい。西がA氏に鈴木の消息を聞かれても「今は日本にいません」とか「鈴木は1DKのマンションで頑張っているので、長い目で見て下さい」と言って誤魔化し、あるいは事務所で紀井がかかって来た電話を取り、鈴木の所在を問われ、鈴木が傍にいたとしても、不在であるとか「今は海外に行っていて連絡がつかない」と言い、絶対に鈴木の所在を明らかにしない工作を周囲に徹底していた。その陳述書が証拠として提出されていた。品田裁判長は、証拠を精査しておらず、最初から排除しようとした可能性が高い。
鈴木は平成10年5月31日に親和銀行から100億円以上の融資を不正に引き出した特別背任の容疑で警視庁に逮捕され、その後起訴されたが、保釈中だった身で株取引を西と共に実行し、インサイダー取引や金商法違反、外為法違反、脱税などの違法行為を繰り返した。そして株取引の利益を独占するために10人前後にも及ぶ周辺関係者を犠牲にした結果、自殺に追い込んだり生死不明の行方知れずにした。
こうした犯罪疑惑にまみれた鈴木の本性に品田裁判長が何ひとつ疑念を持たなかったことは有り得なかったはずだが、判決には一切反映されていない。それが、品田裁判長の故意性を疑う重大なポイントになっていることから、改めて品田裁判長が排除し看過した鈴木の本性や証拠類の信憑性を検証することで判決がいかに過っているかを指摘する。
鈴木が主導した株取引の実態を知るには、西が記録した「鈴木義彦がユーロ債(CB)で得た利益について」と題するレポートがあり、また同じく西が作成した「鈴木義彦との出会いから現在」が明らかにしている。それだけではない。株取引の実行を裏付ける証拠は他にもいくつも法廷に提出されていて、鈴木が取得した株の売り抜けをほぼ全て任されていた紀井氏が、各銘柄の株取引で得た利益とその総額を「確認書」という書面にまとめ、さらに鈴木が利益のほとんどを海外に流出させ密かにプライベートバンクに隠匿している事実を法廷で証言した。また、「合意書」が交わされた直後の平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言って、A氏の会社に15億円を持参した。この時点で、宝林株取引で得られた利益は50億円だったが、鈴木がA氏に渡す分配金を10億円としようとしたのに対し、西が反発して15億円にした。ただ、合意書に基けば、鈴木と西は株取引の収支をA氏に報告し、一旦は50億円をそっくりA氏に渡さなければいけなかったが、鈴木と西は自分たちの都合で15億円を持参することを決め、正確な収支の報告をしなかった。A氏はその15億円を「合意書」に基づいて5億円ずつ分配すると考えたが、西と鈴木が取り分をA氏への借金の返済の一部に充てると言ったことから全額を受け取り、そのうち1億円を心遣いで「鈴木さんと分けなさい」と言って西に渡した。そして翌7月31日、西と鈴木がA氏の会社を訪ね、15億円の処理を確認した。その際に、西と鈴木が5000万円ずつを受け取ったことに礼を述べた。
その後、鈴木と西は株取引の利益を2人で分配する密約を交わし、A氏には具体的な報告も利益金を持参することもしなかった。その後、和解協議が行われるまで、A氏は完全にカヤの外に置かれたのだった。
平成18年10月16日の和解協議で、鈴木が西に「合意書」の破棄を執拗に迫り、その報酬として10億円を複数回に分けて紀井氏から西の運転手をしていた花舘聰氏を経由して西に渡したことを認めた。そして、その場で「和解書」が作成されたが、その後の約1週間の間に鈴木が何度もA氏に電話で連絡を取り、「和解書」で約束した支払約束を追認するとともに、株取引の買い支えで蒙った損失を「合意書」に基づいて補填しなければいけないと発言していた。さらに和解協議から1週間後の10月23日に鈴木が単独でA氏の会社を訪ね、支払を約束した70億円の支払方法を具体的に語っていた。しかも、宝林株について言えば、宝林株で約160億円という巨額の利益を獲得したことで、鈴木が西を巻き込んで「合意書」を反故にすることを企んだのは間違いなく、「利益を二人で折半しよう」と西に持ち掛けた。すると、西はその誘いに目がくらんで鈴木と密約を交わし、その後はA氏に対して、はぐらかしの対応ばかりをするようになり、A氏は株取引の実態が掴めなかったのが真相であった。
こうした合意書に基いた株取引が実行されていた事実経緯と証拠類は挙げればいくつも出てくるのだが、品田裁判長はそうした事実関係の検証を完全に怠り判決に反映させなかったのである。
鈴木の主張が嘘だらけであった事実は、個々に挙げればキリがないが、法廷での主張や証言が二転三転すれば、裁判官は不信を抱き証拠として採用しない、というのが通例であるにもかかわらず、判決を見ると真逆の結果となった。それは、いったい何故なのか? 裁判官が正当な判断能力を行使せずに、何らかの思惑で判決を導くことはあるのか? A氏の提起した貸金返還請求訴訟で最大、深刻な疑問は、まさにそこにあった。鈴木の証言が嘘だらけで、しかも二転三転させても平然としている、その典型的な例が宝林株取得の資金3億円を提供したのが誰だったのか? という点である。
ロレンツィ社が保有していた宝林株800万株の買取りについて、鈴木は「買取りではなく、海外の投資会社がイスラエルの大株主ロレンツィ社から、800万株を1株20.925円でバルサン(バオサンが正確な表記)に300万株、トップファンに250万株、シルバートップに250万株が譲渡された」と主張した。併せて、その購入代金をA氏が出したという事実も否認した。しかし、西が株式買取りの作業を全面的に行った事実を指摘したことから鈴木の主張が二転三転した。また、株式の購入資金についても「株式の買取り企業が直接出した」という主張が途中から「自分の金を出した」とすり替わり、さらにその調達先も「ワシントングループの河野博昌」からと言い換えられ、全く辻褄が合わなくなっていった。前記の外資3社は鈴木がフュージョン社を介して用意(取得)した、実体のないペーパーカンパニーであり、紀井氏がその事実を明確に証言している。前記の外資3社が大量保有報告書を金融庁に提出するに当たっては、買取資金の出所で「紀井義弘からの借入」という虚偽の記載を行って、常任代理人の杉原正芳弁護士は当の紀井氏から抗議を受けたが、杉原からの回答は一切無かった。
さらに、和解書について、長谷川がこれを無効にしようとして強調したのが「公序良俗違反」「強迫」そして「心裡留保」であった。それを裏付けるためにA氏が反社会的勢力と極めて親密な関係にあるという虚偽の事実を強調して、鈴木が和解時には一旦は「合意書」の有効性を認めて自署し指印までした「和解書」までも無効にしようとした。そもそも「合意書」の作成では西も同席する中、鈴木が一人熱弁を振るって懇願した。それで実行された株取引を認めたからこそ和解協議があり、鈴木自身が株取引を一部にしろ認めたことから和解書が作成された。ところが品田裁判長はそうした経緯を全面的に無視したのだ。和解書が作成された当日、鈴木は、西が香港で殺されかけた事件で鈴木が犯人に仕立てられそうになり極度の心身耗弱に陥ったという主張に始まり、A氏の会社が入るビルのエレベータが故意に止められ、鈴木が事実上の監禁状態に置かれ恐怖心を持ったとか、A氏の背後に暴力団が控えていて、逆らえば命の危険さえ感じたという虚偽の陳述を平然と法廷で並べ立てたが、それが虚偽であることは、和解書作成後に鈴木がA氏に送った2通の手紙の内容が全てを物語っている。手紙にはA氏に対して「大変世話になった」とか「男として一目も二目も置く人間にこれまで会ったことは無かった」と書いてあるが、強迫されたという人間が書く文言ではない。そして、鈴木と株取引の実態を知る西義輝が自殺してしまったために法廷で証言できないことを悪用して、合意書を無効にしようとしただけでなく、A氏と暴力団との親密関係を「西から聞いていた」と言って裏づけにしたのである。これらの言動はA氏の名誉を著しく棄損する行為だ。鈴木が法廷偽証に問われる可能性が少ないからと言って、鈴木の嘘を増長させた長谷川の行為は弁護士に課せられる「信義誠実の義務」(弁護士職務基本規程)に大きく違反するものだ。
これは、鈴木に請われるままにA氏が鈴木の言い値の3億円で買って上げたピンクダイヤとボナールの絵画(鈴木は絵画を一度も持参しなかった。他に担保に入っていた)を「売らせて欲しい」と言って平成10年5月28日に持ち出しながら、売却代金の支払も現品の返却もしなかった鈴木の詐欺横領に係る事件だが、鈴木はそれを正当化するために、現品を持ち出す半年以上も前に作成された同額の「金銭借用証書」をもって処理されていると主張した。しかし、時期が全く違っているだけでなく、借用書の但し書きには「日本アジア投資の証券1億円を担保にする」ことが書かれており、ピンクダイヤと絵画のことは何も書かれていない。鈴木がピンクダイヤを持ち出す際にA氏に差し出した「念書」にも「預かった」という文言が明記されており、前記の「金銭借用証書」に係る記述は一切なかった。鈴木の主張は過度の虚偽主張と立証に当たるが、品田裁判長はそうした事実関係の一切を無視して、この販売委託の責任は鈴木ではなくFR社にあるとして、問題をすり替えてしまったのである。
これまで見てきたように、鈴木の主張が嘘だらけで矛盾に満ちていることから、長谷川はそれを糊塗して正当化させるために「質問と回答書」(乙59号証)という、内容の全てが長谷川の創作・捏造による陳述書を作成し、証拠として提出した。
この陳述書はそれまでの審理で鈴木が主張した内容で露呈した矛盾や変転を糊塗するために作成されたもので、陳述書の内容はA氏への誹謗中傷に満ち、完済した債務の二重払いを強要されたとまで言及した。A氏への債務を完済したと鈴木が言うのは平成11年9月30日のことだが、平成14年6月27日に鈴木が15億円、西が10億円の借用書を作成し、鈴木は同年の12月24日に10億円をA氏の所に持参した。債務を完済したという鈴木が何故新な借用書を書き、10億円を返済したのか。この陳述書では10億円を「手切れ金だった」と言い、また別の審理では贈与とも言ったが、10億円という金額を見れば、そのような矛盾が解消されるものではない。
鈴木は「平成14年3月頃に呼び出された」というが、A氏は鈴木の電話番号を知らず、かけようが無かった。鈴木を紹介した西を差し置いて鈴木に直接連絡することは過去にも一度もなく、A氏には絶対に有り得ない事であり、その時期、西は志村化工株事件で東京地検特捜部に逮捕された事情もあったから、なおさらだった。また陳述書の内容は鈴木の一方的な話ばかりで、もしA氏が呼び出したというなら、A氏には鈴木に尋ねなければならないことが山ほどあったにもかかわらず、それが全く記述されていなかった。この陳述書がA氏を誹謗中傷することを目的に創作、捏造したものであることが容易に分かる。
品田裁判長による判決が重大な過ちを犯していたことから、A氏は控訴した。しかし、その控訴審でも、野山宏裁判長はA氏側が主張した一審判決の誤りを正す審議の要請には応じようとせず、審理の期間を数か月で終了させ、平成30年11月28日に控訴棄却の判決を下した。野山裁判長が地裁の判決を丸呑みする格好で支持したために、A氏の主張は東京高裁でも通らなかった。いくつもの重大な疑問に対する真実を見極めなければいけないはずなのに、野山裁判長は「一審で審理は尽くされた」として何も審理しなかったのである。これでは高裁(控訴審)としての役割を放棄したに等しく、品田が多くの証拠類を排除して真実から目をそらした結果の判決を不服として控訴したA氏側の申立理由を全く無視したことになる。訴訟に係る高額な印紙代を搾取したと言っても過言ではないほどで、三審制を標榜する意味すら見いだせない。野山裁判長は判決後にさいたま地方裁判所の所長に転任し、令和4年1月に何事もなかったように定年を迎え退官したが、仮に裁判所の上層部からの早期終結という指示があったとしても、疑念に満ちた品田判決を強引に丸呑みして支持する判決を下したことに後ろめたさは無かたのか。
地裁と高裁での判決はA氏の請求を棄却するもので、鈴木に対する疑念には故意に触れないという体裁になっていたから、鈴木の主張が全面的に認められたと同様で、結果的にはA氏の主張を退けるために鈴木の虚偽主張を前提にしたに等しい。
その後、A氏は上告を断念したために、判決は確定したが、このまま品田裁判長が下した判決が事実、真実であってはならないのは当然であり、再審により是正されなければならない。同時に品田裁判長も、令和3年4月に昇格して担当する民事18部の総括という重責を担っているようだが、正当な信賞必罰が見られない裁判所にあっても、品田が単に勤務経験の長さによりところてん式に総括に就いたとは思えず、品田のような出世欲にかられた人間が自らの過ちを何一つ正さずに裁判所内で昇格するのは、まさに組織の腐敗を象徴している。品田が率いている民事18部には4人の裁判官が所属していて、合議裁判では品田が裁判長として指揮を執っているというが、裁判官として正常、公正な判断能力を持たず、身勝手な思い込みや偏向した考えで暴走するのではないかという危惧を、4人の裁判官たちは抱いているのではないか。すでに品田がひどく誤った判決を下した事実が広く知れ渡っている今、品田が部下たる4人の裁判官たちからどれほどの信頼を得ているのか、極めて疑わしい限りだ。
品田が裁判で下した判決のひどさは、裁判所の上層部、ひいては最高裁の戸倉三郎長官にも責任が及ぶほど尋常ではないのである。その事実は、本誌を含むインターネット上の複数の情報サイトやYouTubeの動画を閲覧している、日本を含む世界中の多くの読者、視聴者から際限がないほど多くの非難が寄せられていることでも十分に証明されている。本来なら、品田自身が自らの過ちを認め、裁判官の職を辞するのが筋というものであるはずだが、それをしないというのであれば、裁判所の外からの際限のない非難や糾弾を品田だけでなく裁判所組織全体が受けることになるだけでなく、その汚名は品田が定年で退官しようとも永久に消えるものではないことを知るべきだ。裁判所組織も同様であろう。
長谷川は、鈴木が代理人に委任した平林、杉原の両弁護士とともにA氏から懲戒請求を受けると知るや、あっという間に辞職した。しかし、それでは責任を取ったことにはならない。それどころか、ただ敵前逃亡を企てたに過ぎない。長谷川の行為は弁護活動の許容範囲をはるかに逸脱しているから、償いをするのは当然なのに、今もなお何一つ反省の態度を見せていないのは、卑怯極まりない。
長谷川には鈴木から提示された高額な報酬を得るために、何が何でも鈴木を勝たせるとして取り組んだ作戦でしかなかった。しかし、度を越したやり方は自身が咎めを受けることを知るべきで、長谷川は鈴木の犯罪疑惑の共犯者として、鈴木と共に罪を償う立場にあることは、当然、未来永劫にわたって残り続け、家族や身内にも永久に影響することを認識するべきなのだ。
A氏が提起した訴訟で最も重要だったことは、全く返済されていなかった鈴木義彦はA氏から借り入れた約28億円(元金)を全く返済していなかった。その返済を主な目的にすることでA氏が了承して開始された株取引が密接に関係していた点にあった。それにもかかわらず、東京地裁の品田裁判長は故意に株取引に関わるA氏側の主張や多くの証拠類を全面的に排除して認めなかった、という重大な過ちを犯した。それを誘発したのは鈴木の代理人を務めた長谷川幸雄弁護士で、長谷川が徹底して行ったA氏に対する誹謗中傷を品田裁判長が採用して、株取引の事実を排除する根拠にしたのは判決からも明らかだった。(つづく)